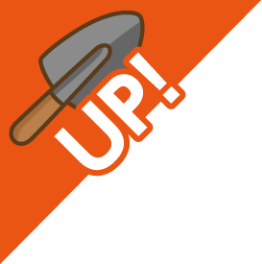WORK IN PROGRESSただいま発掘中!
栗橋宿跡第9地点 (久喜市)
この遺跡について
読み方くりはししゅくあとだいきゅうちてん
場所久喜市栗橋中央二丁目3491-2他
調査期間平成30年4月1日~平成31年3月31日
主な時代近世
遺跡の概要栗橋宿は日光道中(街道)の江戸から7番目の宿場です。JR宇都宮線栗橋駅の東約1㎞の利根川沿いにあります。第9地点は、宿場の町屋が立ち並んでいた区域にあたります。昨年10月から開始され、現在は引き続き第二面(江戸時代後期)を調査中です。
更新日:2019.3.1
更新日:2018.7.1
更新日:2018.10.1
更新日:2018.12.1
更新日:2019.1.1
栗橋宿跡の調査もいよいよ終盤、2月3日(日)には、最後の遺跡発表会を予定しています。発掘現場は、江戸時代の人々が繰り返し掘ったり埋めたりした穴の跡が重なり合っています。穴の中からは当時の暮らしぶりを彷彿(ほうふつ)とさせる遺物の数々が出土しています。
更新日:2019.3.1